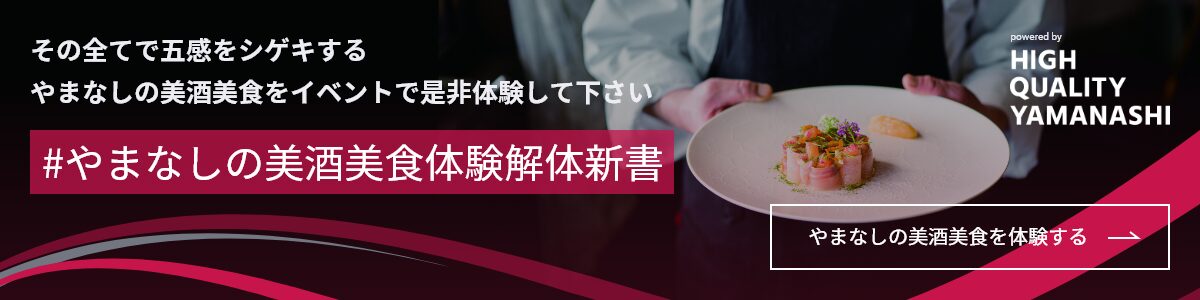皆さんは「樹上完熟」させたフルーツを食べたことはありますか?
樹になったままじっくりと熟され、芳醇な甘さと香りをまとったフルーツは、食べ頃の短さゆえに流通が難しく、産地でしかなかなかお目にかかれない代物です。
そんな「樹上完熟」のフルーツを贅沢に使った極上のスイーツを食べられるのが、山梨県立博物館内にあるカフェ「Museum café Sweets lab 葡萄屋kofu」。
このミュージアムカフェは、県内生産者から直接買い付けた旬のフルーツを、最高の形で味わえるよう設計された特別なカフェなのです。
今回は、ミュージアムカフェのオーナーとメニューを手がける有名パティシエに取材。生産者の思いを大事にする取り組みと、そこから生まれる山梨スイーツの魅力に迫ります。
INDEX
博物館で絶品スイーツが味わえる! 白い空間が引き立てる、旬のフルーツの色彩と風味

「Museum café Sweets lab 葡萄屋kofu」(以下、ミュージアムカフェ)は、甲府駅から車で約25分の場所にある山梨県立博物館の入口横に2023年オープンしました。
店内に一歩足を踏み入れると、白を基調とした洗練された空間が広がっています。ガラス窓から差し込む柔らかな光が全体を包み込んでいて、室内なのに思わず深呼吸したくなるような開放感があります。
この白で統一されたインテリアには、特別な体験になるよう明確な設計意図が込められています。博物館の展示を見て回り、頭をフル回転させた来館者が、何も考えずにゆっくりとくつろげるように。フルーツの色彩を最も美しく引き立てる舞台になるように。
そして、このミュージアムカフェで提供されるのは、山梨県産のフルーツをふんだんに使ったスイーツたち。地元の生産者から直接買い付けたフルーツの鮮度は抜群で、味も格別です。オープン以来、県内外から訪れるたくさんのスイーツ愛好家を魅了し続けています。

実はこのミュージアムカフェ、「山梨スイーツ」の魅力を県外に発信していく使命を持った重要な拠点であり、生産者とパティシエの交流・育成の場にもなっています。その独自の取り組みや、「山梨だからこそ提供できるスイーツの魅力」について、オーナーである古屋浩さんに話を伺いました。
一番美味しい状態を味わってもらいたい、地元出身のオーナーが引き出す山梨フルーツのポテンシャル

▼古屋浩さん
株式会社プロヴィンチア代表。山梨県韮崎市出身。食品の卸売会社での営業、商品開発などを経て独立。ブドウの加工品専門店「葡萄屋Kofu」、「葡萄屋kofuハナテラスcafé」などを展開。2023年に山梨県立博物館敷地内に「Museum café Sweets lab 葡萄屋kofu」をオープン。
どこよりも美味しいフルーツを、最も美味しい状態、最も相応しい調理法でお客様に提供したい――そんなこだわりを持つ古屋さんは「メニューは2〜3週間で入れ替わることもある」といいます。県産フルーツでメジャーなモモやブドウだけでなく、ユズやブラッドオレンジなど、県産としてはあまり認知されていないフルーツも使用。その理由について、古屋さんは次のように語ります。
古屋さん(以下敬称略):このカフェを通して伝えたいのは、山梨のフルーツが持つ本来の魅力です。それを実現するには、生産者と徹底的に対話をして、彼らの”本音”を聞き出すのが不可欠なんですね。
生産者と付き合いがあると、よく「こっちが人気だけど、本当はこの品種も食べてほしい」「見た目は良くないけど、この状態が一番美味しいんだ」といった話を聞きます。一番お客さんに食べてもらいたいフルーツが、商品規格や流通などの都合でなかなか市場に出せない……そんなジレンマを抱えているんです。

古屋:私たちは、そういう“届けたいけど表に出しにくい最高のフルーツ”が日の目を浴びないまま旬が過ぎ、破棄されるような事態を、なんとか阻止したいと思っていて。生産者のもとに何度も通って、彼らの思い、本当に扱いたいフルーツ、出したい時期などを丁寧に聞き取りながら、それらを最大限に生かせるようなスイーツを開発しているんです。逃したくない最旬を大事にするからこそ、メニューの入れ替わりも激しく、そこはかなり苦労していますね(笑)
農家が届けたい“最高の桃”、なぜ市場に出回らない?
生産者が一番食べさせたい状態のものが、お客様に届いていない――その対象の筆頭に上がるのが、山梨が誇る特産物の桃だと、古屋さんは続けます。一般的に市場に流通している桃は、輸送間の日持ちを考慮して、硬い状態で収穫・出荷されています。しかし、本当は「樹上完熟」といって、樹になっている状態のまま完熟させた桃がベストなのだそうです。

古屋:樹上完熟させた桃は、肉質が細かく、噛むと果汁がほとばしり、本当に美味しい。私も初めて食べたとき、柔らかすぎない絶妙な食感とジューシーさに衝撃を受けました。そこまで完熟させきってしまうと足は早く(フルーツが腐りやすい事)なるし、見た目も少し悪くなるものも多くなるので、市場にはほとんど出回りません。
ミュージアムカフェでは生産者と密に連携しているからこそ、樹上完熟した最高の桃を使用したスイーツを提供できています。これは本当に全国でも“ここでしか出合えない逸品”だと自負しているので、ぜひ一度食べに来ていただきたいです。
こうしたミュージアムカフェの取り組みは、地元の生産者にも大きな好影響を与えています。今までは売れ残りや廃棄を恐れて地元の無人販売所で安く売るしかなかったフルーツに、“スイーツ用”という新たな活路が生まれました。
そのおかげか「生かしてくれる場所があるのなら、もう少し熟すまで待ってみよう」「もう少し別の品種も少量から育ててみよう」などと、生産者が新たな挑戦をしやすくなっているのだとか。また、自分たちの作ったフルーツが使われたスイーツを「美味しい!」と食べてくれるお客さんを間近で見られることが、さらなる仕事のモチベーションアップにもつながっているそうです。
交流から新たな風を生む、山梨フルーツ版の”トキワ荘”を目指して
古屋さんはミュージアムカフェを拠点とし、パティシエと生産者の交流機会を積極的に作っています。また、地域のパティシエや料理人を対象とした「フルーツ活用講習会」「若手パティシエ育成プログラム」も、県の委託を受けて開催。そこに地元の生産者を招き「山梨県のスイーツ業界を関係者みんなで盛り上げていく空気を醸成したい」と意気込みます。

古屋:生産者とパティシエ、さらには大学や研究機関などの有識者が集まり、交流し、対話の中から新しいものが生まれていく――そんな山梨フルーツ版の”トキワ荘”のような場所にしていきたいですね。最高のフルーツには、人を動かす力があります。僕もそうやってここまで動かされてきた人間の一人です。
これからも生産者の本音や悩みに寄り添いながら、地域のソリューションにもつながるような商品づくりを目指し、関わる誰もが幸せになれる仕事をミュージアムカフェで生み出し続けていきたいです。
銀座の名店シェフが山梨のフルーツに魅せられるワケ
古屋さんに引き続き、ミュージアムカフェの魅力を語る上で欠かせない存在が、グランシェフを務める金子博文さん。都内の有名店でのシェフを務めながらも山梨に何度も足を運び、古屋さんや生産者たちと共にスイーツメニューを編み出してきました。
ここからは、そんな金子さんがミュージアムカフェにかける思いについて、お話を伺っていきます。

▼金子博文さん
元銀座ウエストシェフ (2025年2月末で勇退) 。長年にわたり日本各地の生産者と交流を深め、素材の魅力を活かしたスイーツづくりを追求している。「Museum café Sweets lab 葡萄屋kofu」ではオープン時からグランシェフを務め、メニューの開発を担当している。
金子さんは以前から各地の生産者と交流を深めてきましたが、特に山梨に惹かれた理由があります。
「以前からいろいろな地域の生産者と関わりを持つ中で、『もっと産地に直接的に貢献できるような仕事がしたい』『現地で出てくる素材にタイムリーに向き合いたい』という気持ちが膨らんでいました。ミュージアムカフェはまさにその願いを実現できる場所だなと感じたんです」
金子さんは愛媛県の出身で、祖父母が柑橘農家を営んでいました。幼い頃から農業に親しんでいた影響もあって「素材があるから、私たちの仕事がある」という思いを強く持っているそうです。産地に足を運び、生産者と直接関わることで彼らの苦楽を理解すること――そうした過程を大切にするスイーツには「魂が宿る」と、金子さんは考えています。
生産者との対話から生まれるスイーツづくりの秘密

金子さんのスイーツづくりの特徴は、生産者との対話から始まることです。決まったレシピや商品ありきではなく、生産者の課題や思いを起点にメニューが生まれます。
金子さん(以下敬称略):基本的に、扱うフルーツを見る前に「こういうスイーツを作ろう」というイメージを持たないようにしています。生産者の畑を訪ね、話を聞くと「見た目が悪くて生食用として出荷できないが、味は良い」「知名度がなくてあまり売れない」など、それぞれの悩みを打ち明けてくれます。そういった生産者の課題を起点に、彼らの思いが最もいい形で成就するようなレシピを考えています。
山梨での活動を通じ、金子さんは「新たな発見がたくさんあった」といいます。たとえば、農園の周辺に生えているハーブや花を組み合わせることで、スイーツにその土地のテロワール(地域性)を表現できることに気づいたそうです。
金子:南アルプスの山中で見つけた和ハッカをモモのスイーツに取り入れたり、ユズの種など普通なら捨てられる部分から香りを引き出したりしています。そうした工夫をしていくと、山梨の風土すべてを一皿で存分に味わえるデザートが生まれるのだなと。私もここでの仕事を通して、とてもいい勉強をさせてもらっていますね。

金子さんが考案してきたメニューには、見た目の美しさや美味しさに留まらない魅力があります。そこには「自分達のフルーツの価値を再認識してもらいたい」という生産者の願いが込められているのです。
金子:生産者の皆さんにもスイーツを食べてもらうことで、「自分たちが努力して育てたフルーツがこんな形で表現されるんだ」「こんなに価値があるものだったんだ」と気づいてもらえたらうれしいですね。
山梨のフルーツは生で食べるイメージが強いと思いますが、それをスイーツにすることで、また違った魅力を引き出せます。ミュージアムカフェでは、旬のフルーツを使った、ここでしか食べられない特別なスイーツを提供しているので、季節ごとに訪れる楽しみがあります。ぜひ、生産者の「これこそ食べてほしい」という思いがこもった品々を、体験しにきてください!
四季折々の山梨フルーツを堪能する楽しみ——訪れるたびに新しい発見がある特別な場所へ
生産者とパティシエの対話から生まれる至高のスイーツ。「Museum café Sweets lab 葡萄屋kofu」は、山梨ならではの魅力的なフルーツを再発見し、その土地の風土とともに表現する、新たなスイーツ文化発信拠点です。
桃、ブドウ、さくらんぼにはじまり、ユズ、ブラッドオレンジなど、山梨には四季折々のフルーツがあります。それぞれの季節で異なるフルーツを使ったスイーツが登場するため、何度訪れても新たな発見と感動があるでしょう。
また、山梨県では、県産フルーツを使用したスイーツの魅力を伝え、パティシエの技術向上を目的として「若手パティシエ育成プログラム」や「やまなしスイーツコンテスト」といった取り組みも実施しています。山梨をフルーツだけでなく「スイーツの名産地」としても確立すべく、さまざまな活動が展開されているので、興味のある方はぜひ次の関連記事もチェックしてみてください。
▼関連記事
【熱きパティシエの挑戦】フルーツ王国・山梨の甘い未来をつくる「やまなしスイーツコンテスト2024」密着取材! – 食楽web
「山梨産フルーツへの思いを込めた若きパティシエたちの挑戦。【やまなしスイーツコンテスト2024】結果発表」– 食楽web
山梨の旬のフルーツを使った贅沢なスイーツを求めて、次の週末は山梨県立博物館へ足を運んでみませんか。四季折々のフルーツが織りなす産地でしか味わえない感動の一皿が、あなたを待っています。
▼関連リンク
Museum café Sweets lab 葡萄屋kofu
山梨のフルーツで新しいスイーツを開発!若手パティシエ育成プログラム