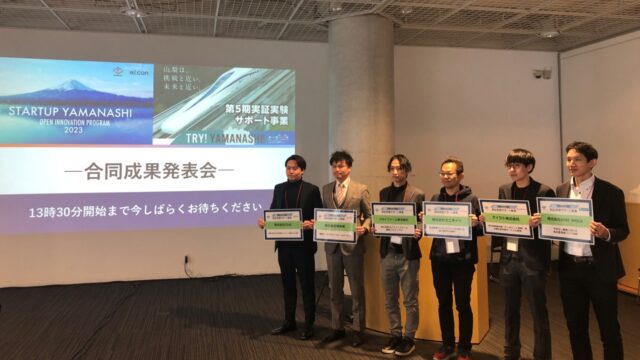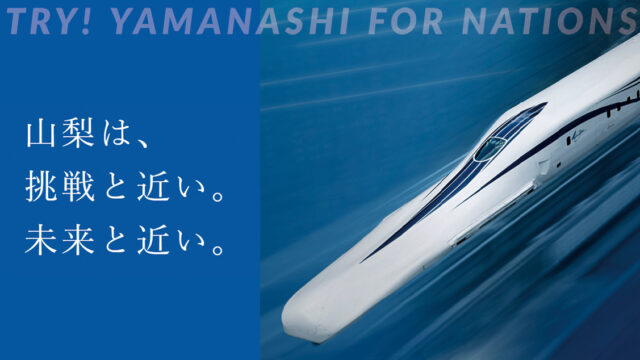実証実験だけやっておしまいでは、世の中の課題は解決できない!
「テストベット(実証実験)の聖地」山梨県では、ドローンによる過疎地への物流、視覚障がい者・高齢者が気軽に外出できる歩行アシスト機器など、数々の社会課題解決に向けた実証実験をサポート、主にベンチャー・スタートアップ企業を受け入れる環境を整えてきました。
そして2024年度、長崎知事が掲げる「挑戦に近い山梨」というスローガンのもと、スタートアップやものづくりといった枠組みにとらわれず、あらゆる「新たな挑戦」とその実現を支援するためスタートしたのが「新事業共創プラットフォーム TRY!YAMANASHI!」。ベンチャー・スタートアップだけではなく山梨で根を張って事業をしている人、新たに事業を考えている人、「山梨で何かやりたい!」という人たちの受け皿となるべく、「山梨で頑張る人たちの応援団」として新規事業創出への挑戦を全面サポートします。
これまでの実証実験で蓄積したノウハウを生かし真に社会課題を解決するため、ビジネスとしてどう社会に根付かせていくのか、熱意ある企業が集まる場を育て応援の環をどう育てていくのか……本記事では、「新事業共創プラットフォーム TRY!YAMANASHI!」の活動の一環として毎月開催をしているピッチイベントにフォーカス。「テストベットの聖地」の中で生まれている挑戦と熱意ある企業をご紹介いたします。
INDEX
“挑戦者”の想いが交差するピッチイベント
長崎知事が掲げる「挑戦に近い山梨」のスローガンが形になった「新事業共創プラットフォーム TRY!YAMANASHI!」プロジェクト。目玉の一つは、毎月行われるピッチイベントです。ピッチとは短い時間で自社の製品やサービスを紹介することですが、本ピッチイベントでは山梨県で新事業を起こしたい人、支援したい人が集まり、熱気たっぷりのプレゼンが繰り広げられています。
「ピッチイベントに来ると『こんなに応援してくれる仲間がいるんだ!』と身近に感じられます。だから一歩踏み出す勇気が湧くし、一緒にやろう、困難な課題も乗り越えようと前向きになれるんです。まずは見学だけでも構いませんので、ぜひ足を運んでほしいですね」と語るのは、山梨県職員で本プロジェクトを担当する齊藤政策企画監。
2024年9月に実施されたキックオフイベント(※)以降、10月、11月とピッチイベントを開催。12月19日に行われたピッチでは、3名の“挑戦者”がコアメンバー(※)や観覧者を前に、熱心にプレゼンを行いました。その様子をご紹介したいと思います。
※2024年9月実施のイベント詳細はこちらをご覧ください。
https://www.pref.yamanashi.jp/challenge-g/shinjigyou0925.html
※コアメンバーとは、県内で活動する経済団体や金融機関、学術研究機関、観光・農業・福祉など幅広い事業者や起業家で構成され、挑戦者の支援の中核を担っているメンバーのことです。
視覚障がい者向けのAI歩行アシスト装置を山梨から世界へ
【株式会社マリス creative design 和田康宏氏】

最初の登壇者は、東京都新宿区に本社を構える「株式会社マリス creative design」の代表取締役/CEO和田康宏氏。同氏が披露したのは、視覚障がい者向けAI歩行アシスト装置「Seeker(シーカー)」でした。
視覚障がい者向けのAI歩行アシスト装置「Seeker」とは:
肩にかけるヘッドホン型のAIカメラと白杖に装着する振動機器のセットで、AIカメラが危険を察知すると使用者に振動で危険をお知らせ。独自開発のAIで情報処理を行い、危険察知することが特徴。
視覚に障がいのある方が外出する際、様々な危険が存在します。駅のホームドアが未設置など一般的に知られている危険だけではなく、狭い道路でトラックのサイドミラーが頭部付近にぶつかるかもしれない、といった当事者でないとわからない危険も存在します。「Seeker」はこうした危険をAIで察知し知らせることで、視覚に障がい者がある方の安全な外出・歩行をアシストする装置として開発されました。
開発をした和田氏は3歳の時にお母様が障がい者になられたことで生活が一変した体験があり、「困っている人の課題をなんとかしたい」そんな想いが、このプロダクト開発の原動力になっているそうです。
すでに山梨県で実証実験を重ね、高齢者の歩行アシストへの応用も視野に入れています。「次は本格的な量産化を進めたい」という和田氏。量産設計に向けた製造パートナーや大学との連携を模索しており、「山梨で製造から社会実装まで完結させ、世界にむけてこのプロダクトを発信したい」と熱いビジョンを語りました。
また、テック系に興味のある大学生をインターンとして迎え入れ、貴重な量産設計の現場を共有しながら育成を図りたいと提案。加えて、出資を含むパートナー探しも視野に入れており、「一緒に山梨から未来を変えましょう」と呼びかけました。
株式会社マリス creative design
HP:https://maris-inc.co.jp/
山梨をAI実務活用のパイオニアに
【株式会社First AI 山内悠真氏】

続いて登壇したのは、大阪市に本社を置く「株式会社First AI」の取締役COO・山内悠真氏。同氏は山梨県昭和町出身の22歳で、今も京都大学に通う現役の大学生ながら、すでに教育関連と広告関連の会社を起業。さらに、米国留学中に共同創業したという「株式会社First AI」で、AIシステム開発から、企業向けの生成AI研修などを行なっています。
山内氏が故郷で実現したいことは、「山梨から始まるAI都市への挑戦」。同氏は、以下2つのテーマを軸にプレゼンを展開しました。
- 少子高齢化と若者の地元離れで深刻化する“人手不足問題”
- AI(特に生成AI)を活用して、その人手不足をどう補うか
少子高齢化と若者の地元離れで深刻化する”人手不足問題”
山梨県では少子高齢化の進行と若者の都市部への流出により、深刻な人手不足が発生しています。特に地元企業では必要な人材確保が難しくなり、事業継続や地域経済の発展に大きな障壁となっています。山内氏はこの状況を地域の存続にかかわる重要課題として位置づけました。
AI(特に生成AI)を活用して、その人手不足をどう補うか
その課題解決のため、同社は人手不足の課題を抱える企業のSNS運用やプレゼン資料作成といった業務を業務委託形式で受注。請け負った業務を生成AIを活用して実行し、大幅に業務実行期間を短縮させました。さらに、通常の業務委託と比べコストも3分の1〜半額程度に抑えられ、結果として限られた人数でも業務をこなせるようになり、人手不足問題の解決に繋げてきました。
さらに、課題解決後「実はAIを活用していたんです」と”タネ明かし”をすることで、企業内でAI活用の機運を醸成。具体的に普段自分たちが行なっている実業務でのAI活用方法を見ることで、その実用性を体感。企業側がAI人材の育成やAIシステムの内製化を推進する「コストではなく投資になる」仕組みも提供しています。
また同社では、県内の大学生を生成AIエンジニアとして育成・採用し、県内企業のSNS運用やWebサイト作成などの実務を任せています。この取り組みにより、学生たちに地域課題への関心を持ってもらうと同時に、県内企業の人手不足を生成AIの活用によって解消する道筋を作っています。
山内氏は山梨県をAI先進県にするという志のもと、2025年末までに「県内でAIを活用する企業を現状の10社から50社に増やす」「AI人材として育成した若者を9名から50名に拡大する」という具体的目標を掲げています。その達成のために「県内企業、学生との接点がもっと欲しい」と訴え、山梨県には企業とのマッチングや導入事例を増やすための支援を要請しました。
そして最後に「山梨は流行やテクノロジーが『5年遅れる』と言われていますが、生成AIの分野ではこの遅れをなくし、むしろ山梨がパイオニアとなる未来を確信しています」と、故郷を思う情熱を込めてピッチを締めくくりました。
株式会社First AI
HP:https://website-uo5q.onrender.com/
山梨県民の金融リテラシーを底上げしていく
【一般社団法人「日本金融教育支援機構」平井梨沙氏】

最後にご紹介するのは、東京を拠点に全国で活動する「日本金融教育支援機構」の代表理事 平井梨沙氏。同機構は子どもや若者の金融リテラシーを高めることをミッションに掲げ、親の金融リテラシーが子どもの未来を左右する家庭間格差や、地方で金融教育に触れる機会が少ない為に金融詐欺の被害を受けやすくなるといった地域間格差などを無くすことを念頭に、人生の選択肢を増やす金融教育を実践しています。
お金にはさまざまな力があり、武器にも守りにもなることを子どもや若者に正しく伝えるため、中高生が金融教育を実践する「FESコンテスト」を全国で開催。
「教える立場にたつことが一番の学びである」というコンセプトのもと、中高生が小学生のために金融教育の動画教材を制作し、コンテスト形式で発表する、大学生によって運営されるイベントとして評価され、各地で話題を呼んでいます。
平井氏は、山梨県民は金融商品への理解度が低く、比較検討せず商品を選んでしまう傾向にあるという「金融リテラシー調査」の結果に触れ、「山梨県内で『FESコンテスト』を開き、若い世代から意識改革をしていきたい」と熱い思いを語りました。
一般社団法人日本金融教育支援機構
HP:https://faincation.com/
実証実験から真にビジネス定着するまで!山梨県の“挑戦”はまだまだ続く

今回のピッチイベントでも、登壇者たちの想いに呼応するように、会場の支援者から鋭い質問や温かいエールが飛び交いました。直前に行われたコアメンバーによる定例会議も白熱。進捗報告に加え、次回ピッチのリハーサルを見た上で意見交換やブラッシュアップが行われ、まるで一つのチームのように挑戦者を後押ししている様子が印象的でした。
実証実験だけやっておしまいでは、世の中の課題は解決できない!
真にビジネス定着するまで「新事業共創プラットフォーム TRY!YAMANASHI!」はサポートしていきます。
コアメンバーである金融機関、大学、観光、農業などの専門家がアドバイス!あなたも「新事業共創プラットフォーム TRY!YAMANASHI!」で、支援を受けてみませんか?
本記事で紹介したピッチイベントは「新事業共創プラットフォーム TRY!YAMANASHI!」を象徴するイベントですが、実際の支援の流れは以下のステップになります。
- ホームページの相談申し込みフォームに入力
- 事務局で事前整理・ヒアリングを実施
- 金融機関・大学・観光・農業など各分野の専門家が集う「コアメンバー」で支援方針を検討
- 「TRY!YAMANASHI! Challenge Pitch」でのプレゼンや伴走支援など、本格的なサポート開始
「コアメンバー」には、県内で活動する経済団体や、学術研究機関、観光・農業・福祉など幅広い事業者や起業家など、多彩な顔ぶれがそろっています。新たな挑戦者のアイデアをブラッシュアップし、必要に応じて企業紹介や資金面の相談にも対応します。
支援者側として手を挙げる方々を、オープンなピッチイベントで募っているのも特徴の一つです。
「実はコアメンバー以外にも支援者として応援してくださる方々はたくさんいます。ピッチイベントを見て、『一緒にやりたい!』と名乗りを上げてくれる方がどんどん増えているんです。こうして仲間の輪が広がっていくのを、私たちはとても楽しみにしています」(齊藤政策企画監)
新規募集も随時受付中ですので「新事業共創プラットフォーム TRY!YAMANASHI!」ご興味がある方は以下よりぜひお問い合わせください。
▼新事業共創プラットフォーム TRY!YAMANASHI!オンライン相談窓口
https://www.pref.yamanashi.jp/challenge-g/shinjigyou0925.html
▼相談申し込みフォームはこちら
相談申込URL:https://forms.office.com/r/ZU64TyxbaL
▼ともに挑戦を支援していただけるパートナー登録はこちら
登録フォームURL:https://form.office.com/r/Vr6yZKwiWr